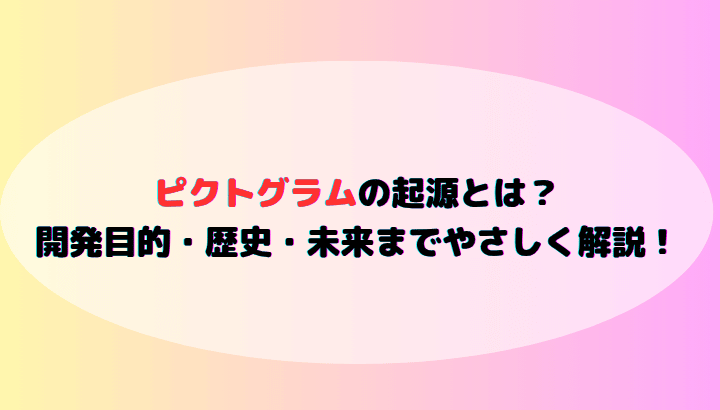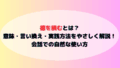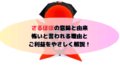駅や空港、道路標識、オリンピック…。私たちの身の回りには、言葉を使わずに情報を伝える「ピクトグラム」がたくさんあります。
この記事では、そんなピクトグラムが「いつ」「なぜ」「どうして」生まれたのかを、わかりやすく紹介します。
ピクトグラムってそもそも何?
視覚記号としての定義とは?
ピクトグラムとは、「情報や意味を視覚的に伝えるための記号」です。簡単に言えば、「見るだけで意味がわかる絵」のことですね。
たとえば、トイレマークや非常口のマークなどが有名です。
絵文字・アイコンとの違いを比較
よく似たものに「絵文字」や「アイコン」がありますが、ピクトグラムは「公共性があり、誰にでも意味が通じる」ことが特徴です。
絵文字は感情表現、アイコンはアプリやボタンの象徴であるのに対し、ピクトグラムは「情報伝達」を目的としています。
なぜ世界中で使われるの?
ピクトグラムは言葉を使わないので、言語が違っても理解されやすいという利点があります。
海外旅行中でもトイレや出口の場所がわかるのは、このおかげですね。
なぜ文字より便利なのか?
言葉は読めないと意味が伝わりませんが、ピクトグラムは「視覚的に一瞬で理解」できます。
時間がない場面や、緊急時などにはとても便利な伝達手段なのです。
日常生活にあるピクトグラムの実例
- 駅の乗り換え案内
- 非常口のマーク
- レストランの「禁煙」マーク
- 道路の横断歩道標識
ピクトグラムの分類と種類
ピクトグラムは、主に以下のように分類されます。
- 案内系:トイレや出口など
- 警告系:危険、立ち入り禁止など
- 誘導系:方向や進行を示すもの
ピクトグラムの起源と歴史を探る
古代文明における絵記号の役割
実は、ピクトグラムの原型はとても古くから存在しています。
古代エジプトのヒエログリフ(象形文字)や、マヤ文明の絵文字も、意味を絵で表すという点ではピクトグラムに似ています。
象形文字とピクトグラムの違い
象形文字は「言葉の音や意味」を絵で表した文字であり、ピクトグラムは「情報を絵で伝えるマーク」として役割が異なります。
近代のピクトグラムの始まり
工業化が進む中で、事故や混乱を防ぐために「視覚で伝える標識」が必要になりました。これが近代ピクトグラムの出発点です。
1964年東京オリンピックがもたらした変化
ピクトグラムが世界的に注目されるきっかけとなったのが、1964年の東京オリンピックです。
言葉が通じない外国人にも案内できるように、日本人デザイナーが多数のピクトグラムを開発しました。
国際標準化とISO
その後、ISO(国際標準化機構)によって、世界共通のピクトグラムが定められるようになりました。
これにより、国や文化を超えて理解される「視覚の言語」として定着したのです。
日本での発展と現在の実用例
現在の日本では、鉄道、病院、学校、観光地などあらゆる場所でピクトグラムが使われています。
とくに災害時の避難誘導などでは欠かせない存在となっています。
ピクトグラムは何のために開発されたのか?
言語の壁を超えるため
多くの人に情報を平等に届けるため、言語に頼らないピクトグラムはとても有効です。
外国人観光客や移住者にも安心して利用してもらえます。
誰でも直感的に理解できる表現
読む力に関係なく、子どもからお年寄りまでが理解できるように作られているのが特徴です。
災害時や緊急時の命を守る手段
停電や混乱の中でも、光る非常口のピクトグラムなどが「命を守るガイド」になります。
視覚障がい者や外国人への配慮
誰一人取り残さない情報デザインとして、ユニバーサルデザインの考え方にも通じています。
公共空間の情報整理として
文字だらけの空間では混乱が起きやすいですが、ピクトグラムで要点を伝えればスッキリと情報整理できます。
現代社会におけるピクトグラムの役割
交通や公共施設での利用
駅のホーム、バス停、役所などで案内として使われることで、混雑や誤解を減らす役割があります。
オリンピックや国際イベントでの役割
世界中から人が集まる場面では、ピクトグラムによる案内が不可欠です。
SDGsとピクトグラムの関係
SDGs(持続可能な開発目標)でも、それぞれの目標にピクトグラム風のアイコンが用いられています。
Web・アプリデザインでの活用
スマホアプリやWebサイトでも、アイコンとしてのピクトグラムが多く使われ、操作性向上に役立っています。
教育・医療分野での広がり
病院での表示、特別支援教育の教材など、配慮が必要な場面での情報伝達に役立っています。
未来のピクトグラムはどう進化するのか?
AIと組み合わせた自動翻訳ピクトグラム
AIの進化により、その場で自動翻訳できるピクトグラムの開発も進められています。
カスタマイズ可能なピクトグラムの登場
個人のニーズに応じて表示内容が変わる「スマートピクトグラム」も研究されています。
メタバースでの記号の役割
仮想空間でもピクトグラムはナビゲーションや情報表示として活躍するでしょう。
ジェンダー表現や多様性対応の進化
誰もが安心して使えるように、ジェンダーニュートラルなデザインが増えてきています。
国際協力によるグローバルな統一へ
将来的には、国境を越えて同じ意味をもつピクトグラムがもっと増えることが期待されています。
よくある質問(FAQ)
Q. ピクトグラムとアイコンの違いは?
ピクトグラムは誰にでも意味が通じる「公共的な視覚記号」、アイコンは機能やアプリを象徴する「操作記号」です。
Q. 誰でもピクトグラムを作っていいの?
自由に作成することは可能ですが、公共施設で使われるものは国際基準やルールに基づいて設計されています。
Q. 国によって意味が変わることはある?
あります。たとえば、手のひらを向けるジェスチャーなど、文化的背景によって解釈が変わるものもあるため注意が必要です。
Q. ピクトグラムの勉強はどこでできる?
デザイン系の学校や通信講座、またはJIS規格やISOなどの資料でも学ぶことができます。
まとめ|ピクトグラムがつなぐ、言葉を超えた社会
ピクトグラムは、ただの「マーク」ではありません。
言葉が通じなくても、緊急時でも、私たちに必要な情報を届けてくれる、まさに「視覚のことば」です。
これからも進化し、より多くの人にやさしい社会づくりの一助となることでしょう。