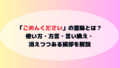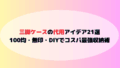「肉じゃがって、東郷平八郎が考案したって本当?」「ビーフシチューの代用品だったって話、どこまで本当?」——そんな疑問を持ったことはありませんか?
家庭の味として親しまれてきた“肉じゃが”には、実はちょっとした「都市伝説」が存在しています。この記事では、そのルーツに迫りつつ、真実とされる歴史や背景をやさしく解説します。
肉じゃがの起源=東郷平八郎?その真相に迫る
・「ビーフシチューを作らせた」説の発端とは
明治時代の軍人・東郷平八郎が、イギリス留学中に食べたビーフシチューの味を忘れられず、日本に戻ってから料理長に「似たものを作れ」と指示。その結果、醤油と砂糖でアレンジされた「肉じゃが」が誕生した——という有名なエピソードがあります。
・明治時代の海軍レシピに残る肉じゃがらしき料理
実際、明治中期の海軍レシピには、肉とじゃがいも、玉ねぎなどを煮込んだ料理が登場しており、現在の肉じゃがとかなり近い形で存在していたことが確認されています。
・ビーフシチューと肉じゃがの違いはここにある
しかし、ビーフシチューはワインやバター、小麦粉を使って煮込むのに対し、肉じゃがは醤油・砂糖・みりんをベースにした和風の味付け。調理法も材料もかなり異なります。
「見た目は似ているかもしれないけど、ルーツとして直結するのは難しい」というのが専門家の意見です。
・このエピソードが“美談”として広まった理由
海軍の偉人が庶民の味を生んだという“親しみやすい美談”は、広まりやすく記憶にも残りやすいもの。学校教育やメディアでも語られたことで、「東郷平八郎=肉じゃがの生みの親」というイメージが定着していきました。
・専門家はどう見る?デマとされる背景
歴史研究家や料理史の専門家の多くは、この説を「脚色された創作」と見ています。肉じゃがという料理は、自然発生的に家庭でアレンジされながら定着したものであり、誰かひとりの発明とは言いがたいというのが現在の主流の見解です。
本当の「肉じゃが誕生」はいつ?
・「肉じゃが」という名称が文献に登場した時期
「肉じゃが」という言葉が文献に登場するのは、大正〜昭和初期。名前として定着したのは比較的新しく、レシピとして確立されてから徐々に呼び名が広まったようです。
・戦後の家庭で定着した“定番おかず”の理由
戦後、日本全国に冷蔵庫やガスコンロが普及し、煮物料理が家庭で手軽に作れるようになりました。肉じゃがは、シンプルな材料と甘辛い味付けで「子どもにも大人にも好まれる味」として一気に広まります。
・当時使われた食材から読み解く時代背景
じゃがいもは保存が効くうえ、安価でボリュームもあるため、戦後の家庭にぴったり。肉も牛・豚・鶏のどれでも応用でき、まさに“庶民の味”として発展していきました。
・関東風と関西風の違いとルーツ比較
関東では醤油が濃いめ、関西ではやや甘めで出汁重視の味付けが多い傾向にあります。この地域差からも、肉じゃがが“各家庭で独自に育ってきた料理”であることがよくわかります。
・現代のレシピとの違いから見える進化
最近では、電子レンジで作れる肉じゃがや、トマトやチーズを加えた洋風アレンジまで登場し、“進化系肉じゃが”としてSNSでも人気を集めています。
都市伝説としての「肉じゃが神話」
・教科書に載らない“もう一つの食の歴史”
こうした“語り継がれるレシピ誕生話”は、日本独特の食文化の一部でもあります。記録に残らないけれど、生活の中で大切にされてきた食の物語です。
・人はなぜ「美談」を信じたがるのか?
人は、感動的な話や人物の功績に結びつけるストーリーに惹かれやすいもの。特に食に関する話は、記憶に残りやすく、家庭でも語られやすいため、都市伝説化しやすい傾向があります。
・ウナギのタレ・カツ丼の由来…他にもあるウソ
たとえば「うなぎのタレは継ぎ足し100年」とか、「カツ丼は負けそうな受験生の縁起担ぎで生まれた」など、あやふやなまま広がった話は数多くあります。
・メディアが「食のストーリー」を作る仕組み
ドラマやグルメ番組、さらにはSNS投稿などによって「話題の料理」に物語がつけられ、やがて“真実っぽく”なっていくこともあります。
・SNSで拡散される“フェイク料理史”の怖さ
バズるために作られたエピソードや、AIによる創作まで混ざっている昨今。情報の出どころを確かめる習慣が、ますます大切になっています。
和食と西洋料理の融合が生んだ奇跡
・明治維新がもたらした“食の西洋化”
文明開化とともに、パン・バター・牛肉といった“洋食”が一気に日本に入ってきました。肉じゃがも、そうした影響を受けながら発展した料理のひとつといえます。
・牛肉とじゃがいもが出会った背景とは?
じゃがいもは北海道での栽培が盛んになり、牛肉は「肉食解禁」後に一般家庭へ。このタイミングが、肉じゃが誕生の土台をつくったとも言えるでしょう。
・シチュー・カレー・肉じゃがの意外な共通点
すべて煮込み料理で、野菜と肉が主役。実は調味料の違いだけで、調理工程はとてもよく似ています。西洋×和風が交わるレシピなのです。
・家庭料理として定番化したタイミング
「材料費が安くて栄養バランスも良い」「作り置きにもぴったり」——そんな理由で、肉じゃがは昭和以降、家庭の定番料理に定着していきました。
・肉じゃがに似ている世界の煮込み料理たち
韓国のチムタク、フランスのポトフ、フィリピンのアドボなど、世界にも似たような“肉と野菜の煮込み料理”は存在します。どれもその国の家庭で愛されています。
「うわさ」でなく「事実」を味わう食育のすすめ
・うわさを鵜呑みにしない大人の知識
「おいしければ何でもいい」ではなく、「どうしてこの味になったのか?」を知ることで、料理へのリスペクトや興味が深まります。
・子どもに伝えたい、正しい和食の歴史
“美談”ではなく、“背景”を伝えることが、本当の意味での「食育」です。家庭での会話のきっかけにもぴったりですね。
・フードロスや持続可能な社会とのつながり
“肉じゃがの日”をつくって余った食材をリメイクしたり、再利用したりすることも、食の大切さを実感する一歩になります。
・“背景”を知れば、いつもの料理がもっと楽しくなる!
レシピだけでなく、その“物語”や“歴史”を知ることで、普段の食卓がちょっと特別なものに変わりますよ。
今夜の献立にも!肉じゃがの魅力を再発見
・“東郷風?”“令和アレンジ?”レシピで楽しむ
あえてビーフシチュー風にデミグラスソースを加えた“東郷風”肉じゃがや、トマトとバジルで洋風に仕上げた“令和肉じゃが”も面白いですよ。
・じゃがいも以外でも美味しい“変わり肉じゃが”
里芋、長芋、大根などに変えても美味しく仕上がります。冷蔵庫の余り物でアレンジするのもおすすめです。
・残ったら翌日アレンジレシピに活用しよう
翌日はコロッケやオムレツ、グラタンの具材にリメイクするのも◎。食材を無駄にせず、飽きずに楽しめます。
よくある質問(Q&A)
Q1. 本当に東郷平八郎が肉じゃがを考案したのですか?
A. 正確には「考案した」という証拠はありません。
東郷平八郎がビーフシチューを希望したという話はありますが、実際の肉じゃがレシピとの関連は曖昧で、後世の創作や美談として広まった可能性が高いとされています。
Q2. 肉じゃがが初めて文献に登場したのはいつ頃?
A. 「肉じゃが」という名前が登場したのは、大正〜昭和初期とされています。
ただし、類似した料理は明治時代の軍隊食や家庭料理としてすでに存在していました。
Q3. 肉じゃがには地域差があるのですか?
A. はい、関東と関西で味付けや具材に違いがあります。
関東はやや濃いめの醤油味、関西は出汁や砂糖を多めに使うことが多いです。また、しらたきや糸こんにゃくの有無、じゃがいもの種類などにも地域ごとの特徴があります。
Q4. 肉じゃがに使うお肉は牛?豚?どっちが正しいの?
A. 地域や家庭によって異なります。
関西では牛肉、関東では豚肉を使う家庭が多い傾向にありますが、絶対的なルールはなく、どちらでも美味しく作れます。
Q5. 余った肉じゃがのおすすめアレンジレシピは?
A. コロッケ、オムレツ、炊き込みご飯、グラタンなどにリメイクするのがおすすめです。
味がしみているので、アレンジしても旨味がしっかり感じられます。
まとめ|「肉じゃがの真実」が教えてくれる食の奥深さ
- 東郷平八郎説は“美談”として語り継がれてきたが、事実とは異なる可能性が高い
- 肉じゃがは、明治〜戦後を経て自然に生まれ、各家庭で育ってきた料理
料理の歴史を知ることで、食卓がもっと豊かに、もっと楽しくなりますね!